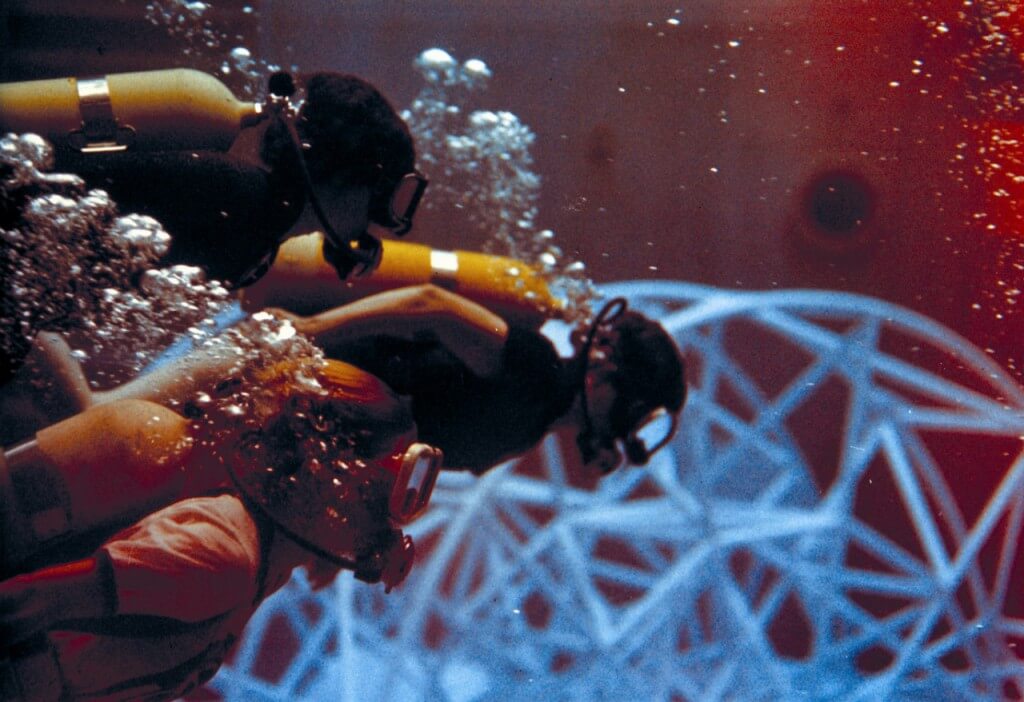デイサービスの指定要件を満たす運営規程表の作成方法
デイサービスにおける運営規定表の位置づけと、書類の作成方法をまとめています。運営規定表は自治体のホームページでダウンロードできますので、ざっと目を通して理解しましょう。
通所介護の指定要件に運営基準があります。
運営基準とはデイサービスを営業していく上の遵守事項です。その運営基準をまとめたものを運営規定表といいます。記載項目は営業時間や責任者の名前などがあげられます。
運営規定表は利用者から見える位置に掲示しなくてはいけません。通常は機能訓練室の入り口付近に貼ります。
運営規定表は指定申請に必要な書類です。なのであらかじめ定めておく必要があります。
当然、運営規程表に書かれていることは運営基準をクリアしていることが求められます。
この記事を読むことで運営規定表を作成する際の注意点を知ることができます。
Contents
通所介護の運営規定表の項目
まず大前提として運営規定表に書いてあることは全て合法でなければいけません。
何を当たり前のことを!
と思う人もいらっしゃるでしょうが、通所介護の指定要件さえ満たせばいいと思っている人も一定数います。
他の法律も全て満たしたうえで有効な運営規定表です。
さて、それを踏まえて運営規定表に書く項目は次の通りです。
以上です。
全て書いてみたものの、自治体のホームページから運営規定表ほダウンロードできます。つまり、ほとんどの項目はどの事業所も共通です。
なので、この中から事業者ごとに記載内容が異なるものを選び作成時の注意点を書きます。
従業者の職種、員数及び職務の内容
通所介護の人員要件を満たす際に兼務で要件を満たすことは一般的です。
兼務している場合は、兼務職名と合わせて記載します。
特に生活相談員はサービス提供時間帯は常にいますので、運営規定表上で英魚時間と矛盾が生じないように注意しましょう。
また機能訓練指導員を配置する場合、どの資格者を配置するのか明確にします。言語聴覚士か理学療法士かで機能訓練の内容は異なるので当然ですね。
運転手や調理を外注している場合は、委託している旨表示します。
営業日及び営業時間
通所介護では営業時間とサービス提供時間は異なります。
営業時間とサービス提供時間をそれぞれ分けて記入しましょう。また延長サービスがある場合、何時まで対応しているのか明記します。
利用定員
単位を分ける場合は、単位ごとの定員数を記入しましょう。
利用料
法定外サービスを提供する場合、実費の価格を必ず記入します。
(例、おむつ代、おやつ代、レクリエーション代etc)
特に外出サービスを提供する場合、交通費はどこまで請求するのかを明記します。距離毎にいくら加算などです。
通常の事業の実施地域
原則、市区町村単位で記入します。
運営規定表の実施地域に書かれているエリアは全て無料の送迎範囲であることを意味します。念のため広く書いておこうとすると大変です。
実施地域に書いていない利用者を受け入れられないわけではないので、適切な範囲で記入しましょう。実施地域外の送迎をする場合、実費の範囲内で交通費を請求できます。
通常の事業の実施地域
事業所の住所がある地域の場合を主な営業地域にする場合、同じ市町村を記入します。
運営規定表の作成時における注意点は以上です。
まとめ
 ・運営規定表は指定申請と同時に必要
・運営規定表は指定申請と同時に必要・自治体のホームページでダウンロード出来る
・利用料はトラブルの素になり得るので細かく明記する。
・運営規定表は機能訓練室の入り口付近に貼る
いかがでしょうか。
初めて運営規定表を作る人からすれば、大変と感じるのではないでしょうか。しかし、記事内にも書きましたが自治体のホームページに運営規定表は載っています。
基本的にはこの記事で言及した部分をしっかり書けば大丈夫でしょう。参考までに東京都が公表している運営規定表をご覧ください。